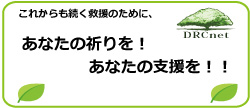災害の神学的理解
キリストさんと呼ばれて~この時代、この地でキリスト者であること
神戸改革派神学校校長 吉田 隆
第2回シンポジウムでは「苦難に寄り添い、前に向かう教会」と、「教会」がテーマとなった。あの震災以降、とりわけ東北にある諸教会は「教会」としての在り方が問われたことは事実である。支援活動において、教会や教団・教派の働き、あるいは超教派や、時には超宗教という協働という協力体制が、あの甚大な被害に立ち向かう中で実に大きな力を発揮した。
しかし、今回は、もっと根本的に一人一人の「キリスト者」の在り方を問いただそうとしている。実際、支援活動の現場では、最終的には一人一人が問題となる。支援物資を一人一人の手によって被災者の元に届ける。あるいは、一人一人の被災者に向き合って何時間でもその話に耳を傾ける。結局は、そうした一人一人との心の通い合いが、支援活動の“質”を決めるからである。そして、この5年間に打ちたてられた個々人との信頼関係が、今もなお継続されている働きに結びついていることは驚くべきことである。
そのようにキリスト者一人一人の働きが為されて行った現場で、被災者の方々の口から「キリストさん」という言葉が語られた。今回のシンポジウムは、その言葉に注目している。キリスト教やクリスチャン一般をさして「教会さん」という言い方はよくされるが、被災支援の現場では、目の前にいる一人一人のキリスト者たちの存在が意味を持ったためであろうか、「キリストさん」と呼ばれることがあった。
震災直後から被災地に何度も足を運んでくださったある牧師が、2011年に発行された雑誌に書いておられた文章が、私の中に深く刻み込まれる印象を残した。
「なにもかもなくなったんだぁ」と家を流されたおばあさんが呟いた。「一人の孫は見つかったけど、下の孫はまだ見つからない。牧師さんきっと見つかるよね」と訴えるおじいさん…。叫びながら流されていく家族、友人をただ見つめるしかなかった人たち。一人一人を訪問し必要なものを聞き、用意ができる限り持っていく。目の前にいる苦しみ痛む人々への直接支援は、共にいることしかない。
訪問した家での出来事である。「あんたら何持ってんのか?」と聞かれた。「何も持ってません。だけど必要なものがあればできる範囲で揃えます」と答えた。「おらなんにもいらねえ。ただあんたら来ると元気になるべ。あんたらキリストさんしょってっからな」と言われた。私たちは何も持っていなくても、キリストを持っているということを教えられた瞬間だった。神様から派遣されることの深みを教えられた。何もできないけれど、キリストがここに立っておられる。そのキリストが被災者に寄り添っておられる。そこに、み言葉がある。「となりびと」とは「寄り添いびと」である。
(『説教黙想アレテイア』特別増刊号「危機に聴くみ言葉」117頁)
まるで、あの「美しの門」でのペトロのように「金銀は私にはない。しかし、私にあるものを上げよう。ナザレのイエス・キリストの名によって、歩きなさい」(使徒3:6。新改訳)という、この信仰、この真理を、私たち自身が被災者の方から気づかせていただいた。いや、むしろそんな大切なことさえも忘れて、目の前の現実に圧倒されて、自分には何もできないけれど何かこの人のためにしたいと思ってたたずむ。そのような姿に対してこそ、「あんたらキリストをしょってる」と言われたのではなかろうか。そこにある神学的な含蓄は何か。日本宣教における私たちの在り方についての見直すべきこと、あるいは新たな可能性ということがそこには無いか。これが、本講演の問題意識である。
2.「キリスト者」という名称~歴史的考察
(1)聖書
ナザレのイエスこそメシヤ、すなわちキリストと信じている人々が「キリスト者(Χριστιανός)」と呼ばれるようになったのは、使徒言行録11:26によれば、異邦人の町アンティオキアにおいてであった。この名称はキリスト教の拡大と共に急速に広まったようで、同じく使徒言行録の26:28では、パウロが伝道したヘロデ・アグリッパという王の口からも「お前はこんな短い時間で私をキリスト者にするつもりか」と語られる。そして、もう一カ所、ペトロの第一の手紙4章16節で、ペトロが迫害下にある小アジアの諸教会に向けて語った言葉の中に、もし「キリスト者として苦しみを受けるのなら、決して恥じてはなりません。むしろ、キリスト者の名で呼ばれることで、神をあがめなさい」と語られる。
「キリスト者(クリスチャン)」という名称は、決してイエスの弟子たち自身が考え出した呼び方ではなく、他の人々、それも「キリスト」の何たるかさえよくわからない異邦人世界で、信者たちを奇異な目で見て、揶揄したり軽蔑したりする名称として生まれたのである。
(2)同時代の聖書外資料(異邦人・ユダヤ人)
聖書外でこの「キリスト者」という名称が用いられた例を挙げれば、例えば、1世紀末にユダヤ人歴史家のヨセフスによって書かれた『ユダヤ古代誌』の中に「彼[キリスト]の名にちなんでクリスティアノイ(キリスト教徒)と呼ばれる族(やから)は、その後現在にいたるまで、連綿として残っている」とある(XVIII:3:3、秦剛平訳)。また、同時代に「キリスト者」という名称が広く帝国内で用いられていたことは、当時のローマ人の文書にも言及されていることから明らかである。
一つは、小アジアのビティニア州の総督であったプリニウスから時の皇帝トラヤヌスに宛てて書かれた有名な書簡である。その中に「キリスト者」として訴えられた人々の取り扱いについてプリニウスが尋ねる文書がある(『書簡集』10:96-97)。そこでは「キリスト者」という名前で呼ばれている人々を、何の犯罪が無くともその名前のゆえに処罰すべきなのか、それとも何か実際に罪を犯した場合にのみ罰すべきなのかという問題が論じられている。歴史家のスエトニウスも『ローマ皇帝伝』の中で、皇帝ネロの時代に「前代未聞の有害な迷信に囚われた人種であるクリストゥス信奉者」に処罰が科せられたと記している(VI:16。国原吉乃助訳)。このネロによる「キリスト者」への迫害については、やはり同じ頃に記された、有名なタキトゥスの『年代記』の中にも出てくる(15:44)。
これらに共通してみられるのは、ローマ帝国内で非合法とされていた「迷信」を信じる「キリスト者」と呼ばれる人々に対する蔑視や嫌悪感、しかしまた他方で、まるで「疫病」のように増え拡がっている事実に対する戸惑いも見受けられる。多くの場合、驚くべき迷信と忌まわしい行為(例えば、人肉嗜食や近親相姦など)との誤解に基づいて検挙されたわけだが、実際尋問してみると犯罪と言えるような行為をしているわけではない。いな、むしろ実際のキリスト教徒たちが善良な人々であることは、周知の事実であったからである。いずれにせよ、ローマ人たちにとって「キリスト者」とは「キリスト」という名前の教祖によって広められた、実に不思議なカルト集団という以上の意味は持たなかった。
(3)初期キリスト教会における用例
やがてこの侮蔑的な名称が積極的意味を持つようになるのは、信者たち自身による。先のペトロの手紙に見られたように、キリストの名で苦しみを受けることは我々にとって本望だとの理解が生まれたからである。そうして、キリスト教徒自身がこの名称を積極的に用いるようになった最初の例は、「キリスト者」という名称の発祥の地であるアンティオキアの監督であったイグナティウスの手紙の中に見られる。殉教するためにローマに連れて行かれる途中でローマの教会に宛てて書き送った手紙で、彼は次のように記す。
私が、外的にも内的にも、力づけられることだけを祈ってください。それは私がただ口で言うだけでなく、(実際)意志するため、(人々に)キリスト者と称せられるだけではなく、実際にそうだと(神に)認められるためなのです。何故なら、(神にキリスト者と)認められたとき、私はまた(人々にもキリスト者だと)称せられうるのだし、この世に見えぬようになったとき、(神に対して)忠実でありうるからです。(3:2)
つまり、「キリスト者」という名称は、自分たちが真にキリストに属する者、キリストの名を負う者であるとの名称なのであり、その名にふさわしく生きることこそが我々のアイデンティティなのだと言うのである。
(4)中世の聖人伝説“クリストフォロス(キリストを負う者)”
この確信が表された興味深い逸話が、クリストフォロスという人物の伝説である。この人は、3世紀に殉教したと言われるが、中世の『黄金伝説』という聖人伝に収められてから非常にポピュラーになった。
それによれば、この人は、もともとカナン人の凶暴な大男であったそうで、最も強い王に仕えようと家来になるが王が悪魔を恐れたために、今度は悪魔の家来になる。ところが、その悪魔がイエスを恐れたために、男はイエスの家来になろうと考えた。そこで、イエスの家来になるにはどうすればいいかと荒れ野で修業をしていた修道士に指示を仰いだところ、「お前のでかい体を使って主イエスに仕えよ」と言われ、近くの流れの激しい河で渡し守りをすることになった。ある日のこと、小さな子供が川を渡して欲しいと男に頼んだ。お安い御用と引き受けたものの、川を進んで行くうちに子どもが重くなり、ついには耐えられないほど重くなって男は川に沈みかける。男は恐れを感じ、「あなたはいったいどなたか」と問うと、「わたしは世の罪を担ったキリストである」との答えがあり、それから彼は「クリストフォロス(キリストを担う者)」と呼ばれるようになったということである。
聖人伝の重要な点は、史実かどうか別にして、庶民の霊性の反映、つまりキリスト者の理想像の反映という側面があることである。世の罪を担われた主イエス・キリストを背負う。それはとてつもなく大きな重荷で、とても我々に担うことはできない。が、同時に「キリスト者」とは、そのように主キリストを担う者である。主イエスと同じようにこの世の苦しみを担う者となることであるという信仰、霊性がそこにはある。
(5)宗教改革における「イミタチオ・クリスティ(キリストにならいて)」
このような中世の霊性は、とりわけ中世末期に聖職者や修道士のみならず一般信徒たちの生活実践を通してヨーロッパに広まったデヴォチオ・モデルナ(新しい敬虔)という信仰運動、わけても「イミタチオ・クリスティ(キリストにならいて)」という霊性に顕著に表れる。
この霊性は、ローマ・カトリック教会においては、有名なイグナチウス・デ・ロヨラの『霊操』に表されたようなイエズス会の霊性につながっていくが、宗教改革者たちの信仰もまたこの信仰運動と無縁ではなかった。プロテスタントにおける「イミタチオ・クリスティ」のモチーフが最も明瞭に表れる一つの例が、ジャン・カルヴァンのキリスト者の生活についての教えにある。彼によれば、「キリスト者」とは「キリストにならう」者に他ならないと言う。
カルヴァンの『キリスト教綱要』第3巻の「キリスト者の生活について」という箇所は、すでに16世紀において『綱要』から切り離されて一つのパンフレットとして出版され、また英語に訳されてイングランドでも広く読まれるようになり、おそらくは後のピューリタンにも大きな影響を与えたと考えられる。そこで、カルヴァンは次のように述べている。
キリストにおいてわれわれを御自身に和解させたもうた父なる神は、そのようにまたキリストにおいて、われわれに「形」を(範例またひながたとして)証印し、われわれがこれを同じ形になるように欲したもう…。われわれは、われわれの生活において子となるためのきずなとして「キリストを表わす」という条件のもとに、主なる神によって子とされる。
(Ⅲ:6:3)
わたしは、福音的な完全さに達していない人をキリスト者と認めないほどに、この福音的な完全さをきびしく要求するものではない…。(しかし)われわれはこの完全さを、唯一熱心に追及すべき目的として、目の前に置くべきである。 (Ⅲ:6:5)
ここには聖書と古代教会以来の信仰がよく表されている。では「キリスト」の名を負うものとしてどのように生きれば「キリストさん」となれるのだろうか。宣教の文脈の中で考えてみたい。
3.宣教における「キリスト者」
(1)宣教と社会的責任~『ローザンヌ誓約』(1974年)
これまでの福音派教会の在り方、とりわけその宣教概念を大きく変えた画期的な文書である『ローザンヌ誓約』の「キリスト者の社会的責任」という項目に、次のようにある。
われわれは…、時には伝道と社会的責任とを互いに相容れないものとみなしてきたことに対し、ざんげの意を表明する。たしかに人間同士の和解即神との和解ではない。社会的行動即伝道ではない。政治的解放即救いではない。しかしながら、われわれは、伝道と社会的政治的参与の両方が、ともにキリスト者の務めであることを表明する。なぜなら、それらはともに、われわれの神観、人間観、隣人愛の教理、イエス・キリストヘの従順から発する当然のことだからである…。われわれが主張する救いは、われわれの個人的責任と社会的責任の全領域において、われわれ自身を変革していくものである。行いのない信仰は死んだものである。
この鮮烈な文章の中で興味深いのは、キリスト者の社会的責任が「われわれの神観、人間観、隣人愛の教理、イエス・キリストヘの従順から当然のこととして帰結する」と言われている点である。事実、愛の業による福音の証はキリスト教の歴史の中でいわば当然のこととして為されてきた。それぞれの時代で苦しみの中に置かれている人々が見えてきた時に、教会やキリスト者はいわば“本能的に”それに反応してきたからである。
(2)キリスト教史における愛の業
ローマ帝国の退廃的な異教社会の中で見捨てられていた女性や赤ん坊や奴隷たちに対して、キリスト者たちは本能的に彼らを守るべく行動した。彼らの愛の業は、当時の異邦人社会にあって驚きをもって受け止められた。やがてヨーロッパ社会そのものがキリスト教化され教会が強大な権力を持つ組織へと変貌すると、そのキリスト教社会において見落とされていた人々に対し、修道士と呼ばれる人たちがイエス・キリストに倣って働くようになる。宗教改革者たちもまた、修道院制度を廃したものの、働きそのものは共同体の中で継承した。そのプロテスタント教会が国家と一体化して近代国家へと変化して行く中で発生した多くの貧困層や孤児たちに対して、やはり心ある教会やキリスト者たちが自主的に救済の手を差し伸べることによって福祉的な働きが為されるようになった。
さらに、近代における海外宣教において、未伝の地へと赴いて行った宣教師たちは現地における様々な社会問題――医療や教育、孤児や病人や障碍者、あるいは身売りをしていた女性たちへのケアなど、宣教地のいわば闇の部分――に光をもたらす働きが福音宣教と一体的に為された。
(3)愛の業の神学的根拠
キリスト者たちやキリスト教会は本能的に人々の痛みと向き合ってきたが、『ローザンヌ誓約』が言及した「われわれの神観、人間観、隣人愛の教理、イエス・キリストヘの従順」という聖書的原則は何であろうか。
①神観~貧しい者の神
弱い立場にある人々を配慮すること、自分を愛するように隣人を愛することは旧・新約聖書の最も重要な愛の戒めの中心にある教えであるが、見落としがちなことは、そのようにお命じになる神が弱さや苦しみの中にある人々と御自分を同一視されているということ。そのような人々の立場の側に御自身を置いておられるということである。我々が信ずる神がいったいどこに目を注いでおられるかを、心に留めねばならない。
②人間観~「あなたがた自身がかつては」
旧約律法には人道的規定と呼ばれるものがあるが、その中にしばしば「あなたたち自身もかつては」というフレーズが繰り返されている。「あなたたちのところに身を寄せる寄留者を大切にしなさい。かつてあなたがた自身もエジプトに寄留していたのだから、その時の苦しみを忘れてはならない」(出22:20、23:9、レビ19:34など)と。
愛の業は「あなたがたは特権的な地位にいるのだからしてあげなさい」という上から目線ではなく、相手と同じ目線で、相手の気持ちを思いはかってしなさいということである。
③イエス・キリストの教え
以上のような神の視点は、よりはっきりした形で主イエスによって教えられている。マタイ福音書25章では、飢えている者・渇いている者・病める者たち、その「最も小さい者の一人」と、イエスは御自分を同一視なさる。そこで問われていることは「何を信じたか」ではなく「何をしたのか」である。もちろんそれは、行いによる救いを教えていることではない。が、主イエスに対する心と「最も小さい者」への心遣いとを一つのこととして教えているのである。
震災を通して何度も思い巡らした「善きサマリア人」のたとえ(ルカ10:25以下)で深く教えられたことは、やはりイエスの視点であった。主イエスの視点が、倒れている人の所にあるという事実である。倒れている人にとっては、そこを通る者の肩書は一切関係ない。助けてくれる人が善い人なのである。イエスは、まさにその倒れている人の視点から見ておられる。いや、イエス御自身が倒れておられるということに気づかされた。
④イエス・キリストの模範
そのような「視点」ということだけではない。イエス・キリスト御自身の模範がある。イエスは、わたしがこの世に来たのは「仕えられるためではなく仕えるため」だと言われた(マルコ10:45)。そして、弟子たちの汚い足を、自ら奴隷のようにして洗われ「師であるわたしがこのように模範を示したのだから、お前たちも同じようにしなさい」と命じられた(ヨハネ13:14-15)。神の御子であられた方が、それに固執することなく低くなられ、実に十字架の死に至るまで従順であられた(フィリピ2:6-8)。このイエス・キリストの僕性(サーヴァント・シップ)ということが、すべてのキリスト者の愛の業の根拠である。
のみならず、イエスの愛の模範には、まさに“存在としての福音”とも言うべき側面があった。イエスの敵対者は「あいつは大食漢で大酒飲みだ」と批判した(マタイ11:19)。実際に、どれほど飲んだり食べたりしたのかは分からない。しかし、イエスは、しばしば飲食をした。独りでではない。「罪人」たちとである。彼らと付き合うことなく、自分を聖く保とうとするなら、そんなことする必要はなかったであろう。しかし、一緒に交わりを持とうとするならどうするのかをイエスはお示しになった。
イエスの所には、罪人と呼ばれた徴税人や水商売の女性たちや、その類の人々が大勢集まってきたという。高尚な教えをされ見るからに近づき難い後光を放つような聖人としてのイエスであれば、彼らは近づかなかったであろうと思う。別に言えば、人間としての魅力が主イエスにあったからこそ、彼らは心を開いたのだと思うのである。イエスに対する(大食漢で大酒飲みという)批判が書かれている箇所に、有名な「疲れた者、重荷を負う者は、だれでもわたしのもとに来なさい」という御言葉が語られている(マタイ11:28)。この御言葉は、したがって、決して単なる人集めのための宣伝文句なのではない。事実を語った言葉なのだ。
本当に主イエスは、疲れた人・重荷を負っている人を招かれた。あるいは自分の方から出かけて行って、人々の魂の疲れを癒された。重荷を降ろしてあげた。何によってか。説教によってか。それもあるかもしれない。イエスの説教はきっと面白いお話だったに違いない。おそらくは、聞いているだけで気持ちが軽くなるような楽しい説教だったのではないか。が、それだけではない。何よりそこに一緒にいて楽しい。嬉しい。このことがあったのであろう。だからこそ、あの徴税人の頭でありましたザアカイも、「ぜひお前の家に泊まりたい」と言ってくださったイエスの言葉に大喜びで反応したのであろう(ルカ19:1-10)。イエスが共にいてくださること自体が“福音”だったからである。
神の国は「義と平和と喜び」であるとパウロは言った(ロマ14:17)。“福音”というのは、そうではないだろうか。喜びでない“福音”などはナンセンスである。そこに一緒にいるだけで喜びをもたらすこと、それが福音である。イエス・キリストの御生涯そのものが“存在としての福音”であったということ。それを忘れてはいけない。
⑤他の新約聖書の教え
他にも、同様の教えが新約聖書には至る所に出て来る。ローマの信徒への手紙の中では「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。互いに思いを一つにし、高ぶらず、身分の低い人々と交わりなさい」と命じられている(12:15-16)。意図的・意識的に、そのような人たちと交わりを持ちなさいと言われる。主イエスがそうだったからである。それは、教会内の交わりにとどまるものではない。パウロは同じ12章で「すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できれば、せめてあなたがたは、すべての人と平和に暮らしなさい」と言っている。神の救い、神の愛は大きい。神の視点は実に広い。小さな教会の中でだけ満たされていればそれで良いという愛は、そもそも愛ではない。少なくとも主イエスに現された神の愛ではないと思う。
この文脈で大変興味深い言葉に、マルコ福音書16章の“結び”におけるイエスの宣教命令がある。そこでは「すべての造られたもの」に福音を告げよと言われていて「すべての人」ではない。この言葉の意味は決して小さくないのではないか。パウロはローマ書8章で、被造物全体が今もうめき苦しんでいる。神の子たちの出現――イエスの福音を信じて、喜びに生きる者たちの出現――を待ち望んでいると言っている(19節以下)。「神の子たちの出現」とは、単純にクリスチャンであればいいということではない。神が造られたこの世界に喜びを回復する、本来の輝きを回復する人たちの出現。この世の中から悲しみや苦しみが無くなるために労し、神の喜びをもたらす人々の出現を、被造世界は今か今かと待ち望んでいるということではないだろうか。
聖書に教えられる「神観、人間観、隣人愛の教理、イエス・キリストヘの従順」を考えた時に、私たちが「キリスト者」として、いわばこのような「キリスト」を表す者として、担う者として、どのような“福音”をもたらすべきなのか、どのような“宣教”をなすべきなのか、自ずと明らかになるように思う。
(4)愛に基づく宣教
『ローザンヌ誓約』の「教会と伝道」という箇所に、次のような文章がある。
われわれは、教会のゲットー化から抜け出て、未信者の社会の中に充満して行く必要がある。犠牲的奉仕を伴う教会の宣教活動の中で、伝道こそ第一のものである。…だが、十宇架を宣べ伝える教会は、それ自身が十宇架のしるしを帯びているものでなければならない。教会は、福音を裏切ったり、神への生き生きとした信仰、人々に対する純粋な愛、事業の振興と資金の調達を含むあらゆる面での誠実さを欠くならぱ、自らが伝道に対するつまずきの石となってしまうことを銘記しなければならない。
「十字架」の福音を宣べ伝える教会あるいは伝道者は、それ自身が「十字架のしるし」を帯びる者、つまりは犠牲的な奉仕を通して人々に対する純粋な愛を表す者でなければならないということである。その「福音」を裏切る諸々の行為や姿勢は、つまずきの石となることを銘記しなければならないと言われる。実に厳しい言葉である。が、真実な言葉であると思う。
“愛”には偽りがあってはならない(ローマ12:9)。本当に愛によって動いているのか、それとも自分たちの目的を実現するために(打算によって)動いているのか、被災者のように弱い立場に置かれている方々は敏感に感じ取る。そのような中で、被災地における支援活動が、今日まで続いていることは、実に感謝なことである。それは、自己実現のためにではなく、本当に目の前の方々を助けたい。この方たちのために何とかしたい。その一心で仕えてきた証しであると、私は思う。
別に言えば、我々が震災後に学んできたことは、単に支援の在り方ということではなく、「十字架の福音」を信じている我々が本当に十字架を負おうとしているのか、自分の十字架だけでなく、世の罪のために苦しまれた御方の十字架を表す者として生きているのか。そのような意味での「福音」を届けようとしているのかという、福音宣教の本質そのものが問われたということなのである。そして、それこそが今、我々が改めて問い直すべきことなのではないかと思うのである。
(5)『ケープタウン決意表明』(2010年)
ローザンヌ運動が2010年、震災の前年に発信した「ケープタウン決意表明」という文書が問うていることは、まさにそのような福音理解なのではないかと思う。この文書全体を貫いているのは「愛」という言葉である。注目すべき文章をいくつか挙げてみる。
包括的な聖書の愛こそが、イエスの弟子としての決定的なアイデンティティであり、弟子であることの「しるし」であるべきなのだと私たちは確認する。…私たちは、愛にあって歩むとはどういうことかを表現するような仕方で生き、考え、話し、行動するためにあらゆる努力をする。この愛とは、神への愛、互いに対する愛、そして世に対する愛である。
(I:1:D/邦訳15頁)
神が私たちに命じていることは、必要を抱えた人を思いやりをもって助けることを通して、神ご自身の性質を反映すること、正義と平和のための奮闘と神の被造物の保護とにおいて、神の国の価値観と力を実際に示すことである。
(I:10:B/邦訳40頁)
Aキリストの弟子として私たちは真理の民であることを求められている。
①私たちは真理を生きなければならない。真理を生きるとは、イエスの顔になることだ。イエスを通して、視界を覆われた心に福音の栄光が啓示される。人々は、イエスのために忠実に愛をもって人生を生きる人々の顔のうちに真理を見出すであろう。
(II:A:1/邦訳44頁)
私たちの召しは、他の信仰を持つ人々の中で、神の恵みの香りに深く満たされて生き、また仕えることで、人々がキリストの香りを嗅ぐことができるようにし、神が良いお方であることを彼らが味わい、また見るに至るようにすることである。そのように体現される愛によって、私たちはあらゆる文化的・宗教的環境において、福音を魅力的なものとするのである。クリスチャンが愛に満ちた生活と奉仕の行為を通じて他の信仰を持つ人々を愛する時、クリスチャンは人を造り変える神の恵みを体現するのである。
(II:C:3/邦訳63頁)
私たちが「イエスの顔」になること。また神の恵み、恵みの福音を「体現」することへの献身が促されている。このような主張が『ローザンヌ誓約』の延長上にあることは明らかですが、もう一方で、いわゆる福音派教会が今日直面している現実が念頭にあるのではないかとも思われる。
昨年日本語に訳されて出版されたフィリップ・ヤンシーの『隠された恵み~“福音”は良き知らせになっているか』(いのちのことば社、2015年)という問題提起の書によれば、米国におけるキリスト教への好感度、わけても福音派に対する評判や信頼は下降の一途を辿っているとのことである。重要なのは、その理由である。福音派の人たちは、「福音」よりは罪意識を人々にもたらしている。彼らは、人々を人間としてよりは伝道の対象として見ている。また、救われている自分たちと滅び行くこの世の人たちという優越心や裁く心で人に接する。人の話に真摯に耳を傾けず一方的に話そうとする、等々である。これらは皆、誤った「福音」理解に基づいているではないかと著者は指摘する。そして、主イエスの「福音」を本来の姿に回復する必要を訴えている。
(6)「福音」の受肉化
かつてよく福音の「文脈化」ということが語られた。しかし、今、私たちが心すべきことは、福音の「受肉化」ではないか。我々自身が「イエスの顔」になる。我々自身が神の恵みを「体現」するということである。それは決して自分の福音を押し付けることではない。キリストも御自分を喜ばせることをされなかった(ローマ15:3)。むしろ「おのおの善を行って隣人を喜ばせ」ること(同15:2)。人々の辛い心や体が回復されて、その顔に笑顔が戻ること。心の奥から再び生きる力が湧き出て来るような喜びが回復されて行くお手伝いをすること。それが、主イエスがもたらした「福音」ではなかったか。もちろん、それが福音のすべてではない。しかし、イエスの「福音」の本質に関わることではなかったかと思うのである。
そのように私たちが人々に真摯に向き合い、その痛みや苦しみに心を寄せ、語る前にまず耳を傾けること。そうすればするほど、その問題の重さや深さに返す言葉もなく、ただ祈るしかできない自分の無力を私たちは嘆かざるをえない。共に泣くしかできない。それでも一緒に生きて行こうと寄り添って行く時、その時にこそ、実は私ではなく、私の中に与えられている神の愛が、その深い恵みが姿を表してくるのではないか。本当の意味で「キリスト」が立ち現われて来るのではないか。そうして初めて、固く閉ざされていた人々の心が、打算に満ちたこの世には無い神の愛に開かれて行くのではないだろうか。
そのような十字架をなぜ「キリスト者」が負うことができるか。それは、主イエス御自身が共に担ってくださるからに他ならない。困難な状況の中でも、なぜ「キリスト者」は絶望しないのか。それは、十字架の彼方にある復活の希望を知っているからに他ならない。東北の被災地だけではない。今日、この国やこの世界を覆っている、とてつもなく重い悲惨に押しつぶされそうになっている人々と共に、十字架を背負って行こうとすること。主イエスがなさったように、その人たちの幸いが取り戻されるため、この世界に喜びを回復するために、希望をもって無力な自分を差し出して行くこと。それが今「この時代、この地でキリスト者であること」の意味なのではないだろうか。
(第4回東日本大震災国際神学シンポジウム講演より抜粋)