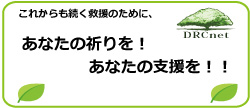被災地での宣教のあるべき姿ー遣わされた教会
3.11いわて教会ネットワーク 佐々木真輝
被災地での宣教について、「〜べき」ということにはためらいがある。そう言い切るには神学的にも実証的にも積み重ねが十分とは言えないと感じるのだ。
しかしながら被災地で教会やキリスト教支援団体が、あるいはクリスチャン個人が取り組んできたことは、私たちが何のためにここに遣わされているのか、この世における教会の存在理由は何なのか、つまり私たちはどのようなことに召されているのかという問いかけと向き合う、神学的で、実際的な営みでもあった。
そうした取り組みを通して、十分な答えと云えずとも、私たちが遣わされている、絶えず痛みを抱えるこの世界での宣教について、尋ね求めていかねばならない視点が与えられたと信じる。
本稿では、ごく簡単ではあるがそうした視点について述べていく。(1)教会が遣わされている世界をどのように見るか、(2)教会は何のために遣わされているか、(3)多様性と公同性をどのように調和させるのか
1.「うめき」のただ中にある教会
被災地における宣教について考える上で最初に確認しなければならないのは、教会が置かれ遣わされている世界をどういう視点で見るか、ということではないかと私は考えている。世界をどう見るかによって、関わり方が変わり、私たちに委ねられている「宣教」の理解が大きく変わると考えるからである。
私たちの世界に度々襲いかかる災害は、人間の築き上げた社会やシステムの脆弱さを明らかにする。しかし災害をもたらす自然自体は、私たちに敵意を示すものではなく、神の被造物であり、本来「良い」ものであるにも関わらず「うめき」の中にある事実を思い起こさせる(ローマ8:19-23)。
その「うめき」は人間自身のうめきに通じるものであり、その中心には被造物の代表たる人間の罪がある(しかし地震と津波が人間の罪がもたらした結果、あるいは「裁き」であるかのような見解には与することは出来ない)。
自然の猛威が人間社会に触れるときに明らかにされる弱さとは、単に地域や社会の抱えるシステムやハードの不完全さというだけでない。社会を構成する人間自身の自己中心性や偽り、弱者への無関心、責任回避、疑い、妬み、といった罪の問題として、あるいは数々の幽霊譚が語られたように、まことの神を知らないがゆえの恐れの問題として浮かび上がったのではないだろうか。私たちが被災地における教会の役割を考えるとき、防災や福祉、社会学的な観点以上に、そうした霊的な現実へのまなざしを大切にしなければならないはずだ。
確かに大規模で悲劇的な状況にも拘わらず、愛他的で感動を覚えるような出来事が数多く起こり、語り伝えられた。しかし一方では闇夜に乗じた窃盗事件が起こり、支援物資を巡る争いや、支援の名を語った詐欺行為すら行われた。多くの被害者を生み出した原発事故は、全貌が未だ十分に解明されたとは言えずとも、不透明さ、無責任さ、不誠実さを多くの人が感じ取ってはいないだろうか。
私たちは、罪ゆえにうめくものとなった被造世界の中に生き、罪ゆえにうめき、傷つけあい、それでいて助けを必要としている人々によって成り立っている社会の中に生きている。弱さは被災者だけでなく支援者の中にもあることは明らかだった。教会は、うめく世界のただ中に遣わされた存在、しかも自身が不完全で弱さを内包した存在なのである。
2.支援と宣教
そうした世界に遣わされた教会の務めは一体何であろうか。私たちはそれを教会論的には「宣教」と呼び、個人的な事柄としては「召し」と呼んで来たかもしれない。
しかし震災があって、にわかに私たちの生活や教会の営みの中に「支援」が入り込んできた。多くの教会や個人が、被災地の惨状を見聞きして心動かされ、ある種当然のことのように「支援」を始めた。
けれども支援活動のごく初期の段階から「支援と宣教」はどのように関係するのかということが重要な問いとして浮かび上がってきた。
私たち3.11いわて教会ネットワークでは、はじめから「支援」と「宣教」を分けずにひとつのこととして理解してきた。痛み悲しんでいる人々に愛を持って寄り添うことは、直接的な伝道ではないけれども、キリストの愛を具体的に表すことであり、そうした関わり方は宣教の重要な土台であると考えたのである。
宣教(伝道)と支援という別々のものがあるのではなく、私たちが遣わされた世界と人々を隣人として愛する、愛のスペクトラムとして捉えたい。私たちは主にある兄弟姉妹にも、求道者にも、支援は必要でも信仰には無関心な者にも、敵対する人々にも、愛をもって関わることが教えられているからだ。そのようにして、多種多様な人々がいる被災地で、実に様々なかたちの支援活動がなされたのである。
しかし、支援活動はすべきこととしても、教会は援助団体ではないのだから、教会の働きには、一般の支援活動とは異なる何かがあるはずである。ペテロが「美しの門」で物乞いに語ったことばは「金銀は私にはないが、私にあるものをあげよう」である。短絡的に捉えると金や食べ物を必要としている人に「支援」をするのではなく「キリスト」を提供すべきだ、というふうに読めなくもない。しかし、教会やクリスチャンの基本的なあり方が隣人愛であるとするなら、ヤコブ書が指摘しているように、必要に応える具体的な働きはないがしろにされるべきではない。それでも、キリストを指し示す教会には、教会ならではの支援のあり方、宣教とぴったり寄り添うようなあり方があるのではないだろうか。私はその「あり方」で最も大切なのは「継続性」だと考えている。
一般の支援団体は時間の経過や新たな災害などの状況の変化によって、支援を打ち切り、他へ移動し、あるいは単に興味を失ったり忘れたりする。だがその地に遣わされた教会はそこにあり続ける。活動内容に変化はあっても、そこにある人々との関係は続く。状況の変化や差し出した支援に対する応答の如何によらず、隣人となり、愛を表す者であり続けることによって、そこに暮らす人々にキリストの恵みを見たり触れたりできるものとして指し示し、ことばによる福音宣教の真実さを生き生きと証明する。教会は使命に召されているだけではなく、その地域へと召されているのではないだろうか。
3.キリストにあってひとつであること
支援の現場では当初から教団教派を超えて、素晴らしい協力関係と交わりが築かれた。私たちが願ったことはこうした交わりが、伝道の協力や教会の建て上という面でも継続することであった。これはクリスチャン人口の割合が未伝部族並みに低いにも関わらず驚くほどの教団教派が存在する我が国の宣教において、乗り越えねばならない課題ではないかと私は感じている。
しかし実際問題としては、支援活動という一時的な働きで協力できたとしても、多様な神学と伝統をもった諸団体が教会開拓や教会形成といった、永続的な実を期待できる働きを共にするには難しさがある。教会観や教会政治のあり方、教会文化の違いはそれぞれのアイデンティティと深く結びついているので、安易な合同や組織的な一致には無理がある。また教会文化を無理に同質化していく必要もない。
ではいかにして諸教会は教団教派の多様性を認め、互いに敬意を払いつつ、なお公同の教会としてひとつになって仕えてゆけるだろうか。
その鍵は地域の教会ネットワークではないかと私は考えている。被災地に限らず、ある地域の宣教のために教団教派を超えた地区教会が協力と交わりのネットワークを形成し、教団教派がそうした地域ネットワークと協力していく。諸教会が教団教派という垂直の関係性だけでなく、ネットワークを通して水平の関係性を持ち、自分たちが遣わされている地域の人々に共に目を向け、共に祈り、共に労していく。そのためには神学の伝統や理解の違いを超えて「福音の核心」に土台を置き続けなければならない。そういう意味では地域の教会ネットワークは多文化共生に似た面がある。それは、地域の人々に特定の教会文化ではなく、福音そのものを提示する助けにもなりそうである。
また教会ネットワークは教団などの垂直的な組織と異なり、流動性をもった組織となる。その関係性を保つのは信条や規則、契約ではなく、キーパーソンとなる牧師などの教会リーダーたちだ。彼らの信頼関係と相互の尊敬こそが生きたネットワークの要であると私は考える。
こうした構図が、多様性を保ちながらも、支援を含めた宣教の一致した働きを可能にしてきたし、これからも可能にするのではないだろか。
(信条や契約が無意味だというのではない。教団組織と地域の教会ネットワークでは組織の成り立ち方が違うということだ)
おわりに
はじめに述べたように、被災地での宣教のあるべき姿と言い得るにはさらに学びと経験が積み重ねられていかなければならない(あるいはその都度、それぞれの現場で問い続けるべきことなのかも知れない)。本稿で触れることの出来なかった他の重要な課題もある。習俗に関する理解と牧会的な知恵の問題、人口減少地域でいかにして教会を建て上げていけるか、すでに高齢化や行き詰まりを覚えている教会をどのように支えるか、高齢者や比較的教育レベルの低い人々も十分に用いることのできる教材の開発などなど、課題は様々である。
東日本大震災はコミュニティーの中の最も弱い存在やシステムの脆弱さを浮き彫りにしただけでなく、教会の課題をも明らかにした。その現場で向き合い、悩み、考え続けて来たことは、きっとこれからの教会のあり方に良きものを残すことだろう。